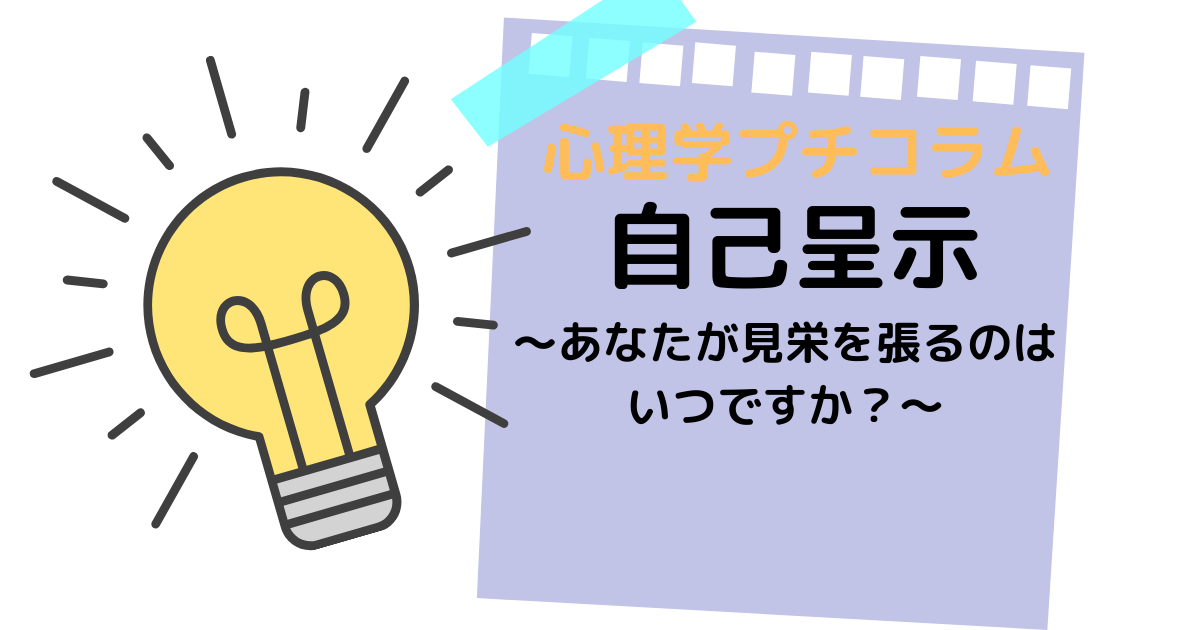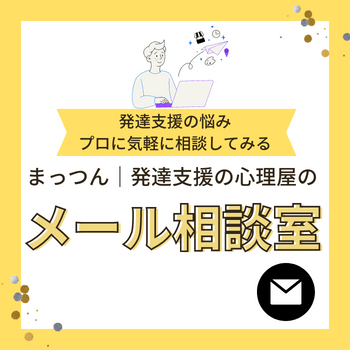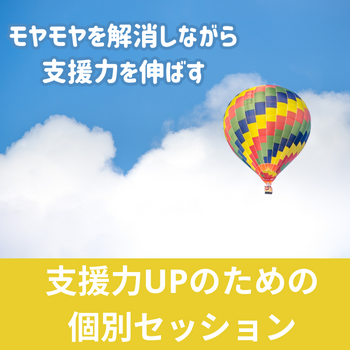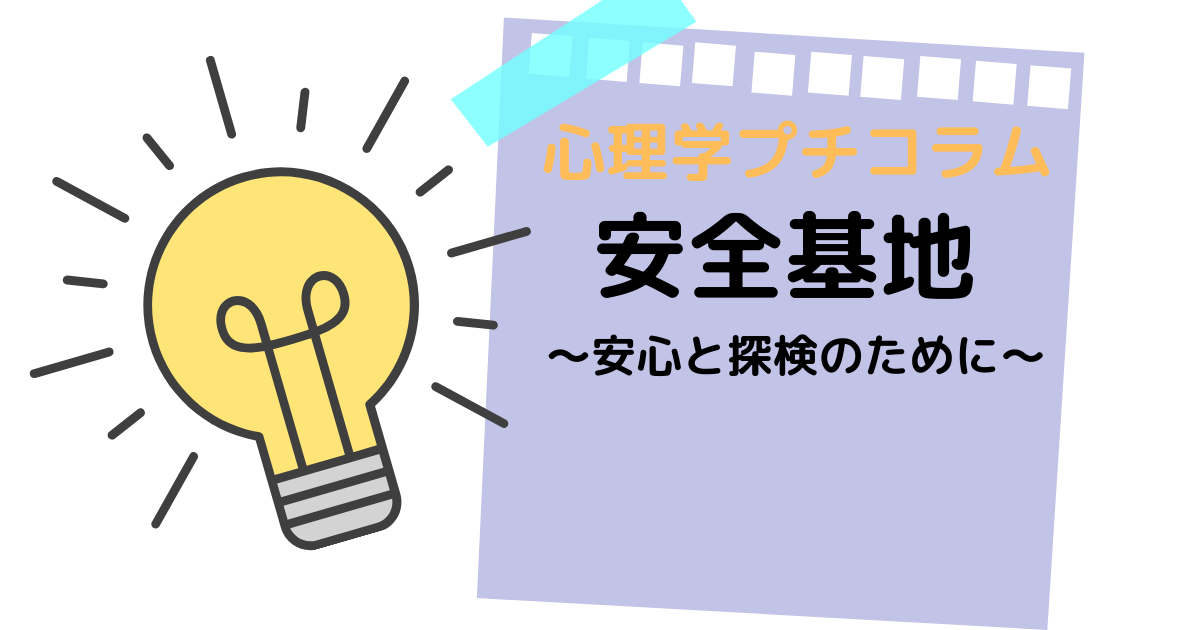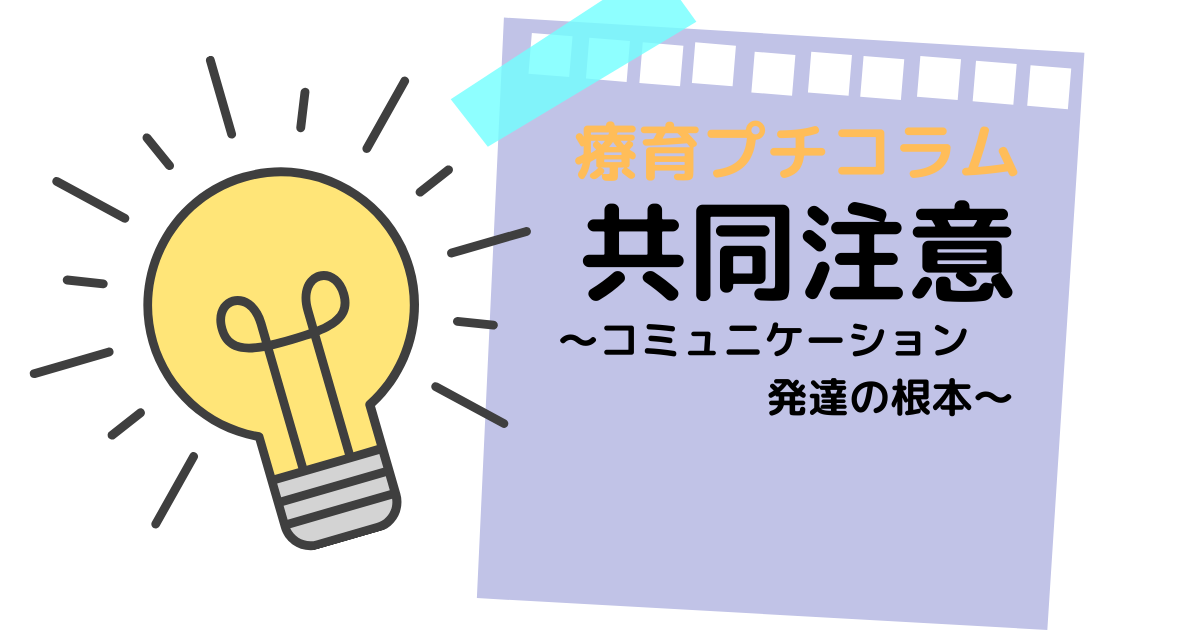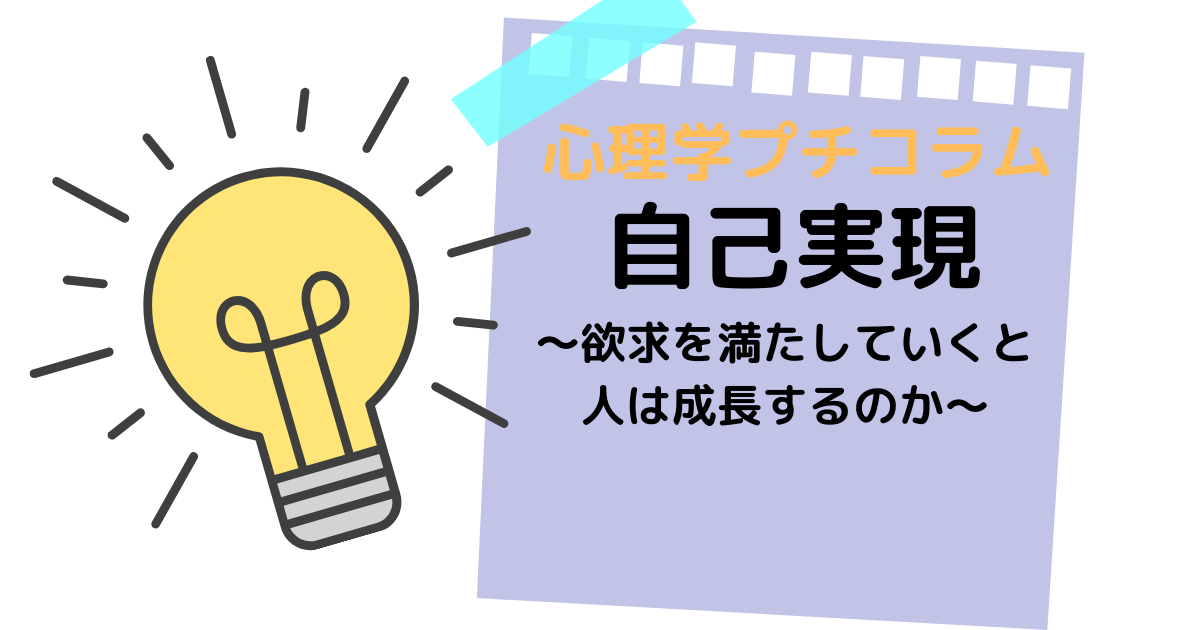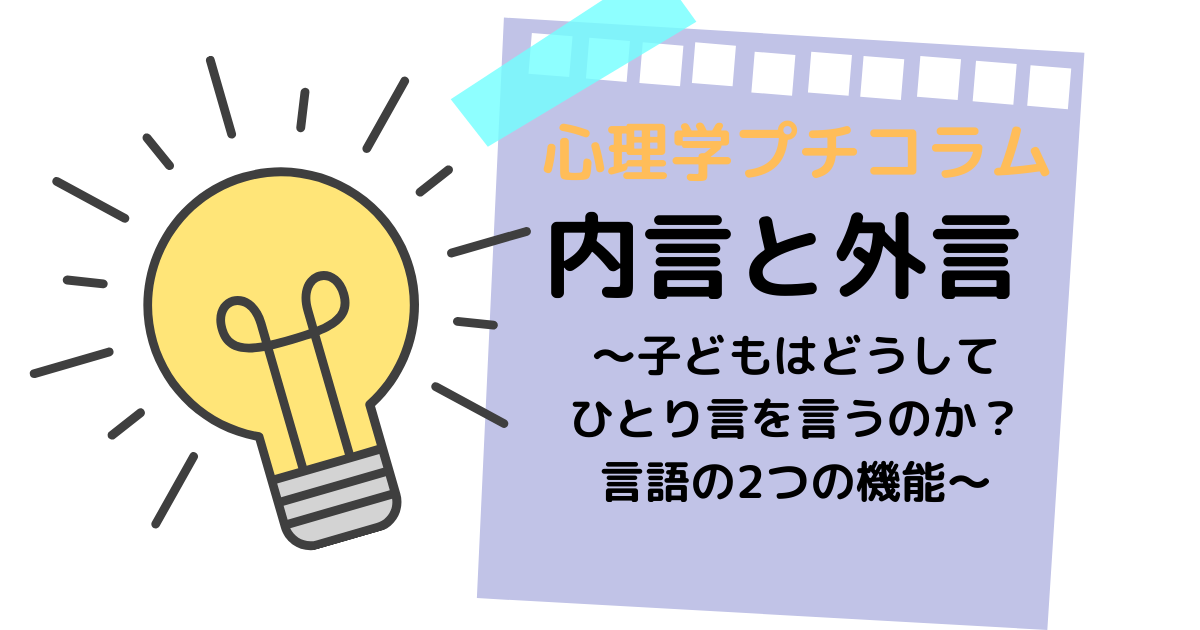【自己呈示】 自己提示と表記されることもある。現実のあるいは想像された社会的相互作用に反映されるイメージを統制しようとする意識的・無意識的な試み。特に,イメージが自分に関連を持つ場合の行動を自己呈示と呼ぶ。
心理学辞典,有斐閣
見せたい自分を見せる―自己呈示
恋をした時,相手に好きになってもらいたくてついつい見栄を張ってしまうことってありますよね。
「いやー,僕はとても優秀でいつも上司からは頼りにされていてね。この間も大きなプロジェクトのリーダーを任されてしまったんだよ~。」…なんて。
うん,こんな感じで自慢されたらちょっと好きにはなれないかも(笑)。
これが今回のテーマ「自己呈示」の普段よく目にする例です。
広い意味では,他者に自分を見せる行為全般を指しますが, 特に,「他者から見られる自分」を操作するための行動のことを,自己呈示といいます。
上の例で言えば,相手の好意的な印象を操作しようと自分の情報を意図的に呈示しています。 まぁ,その効果が吉と出るか凶と出るかは分かりませんが。
自己呈示の種類
自己呈示には,上の例の様な形の他にも全部で5つの種類があります。
- 自己宣伝 自分には能力があるということを見せようとする。 これが,上の例のパターンですね。
- 取り入り 好感が持てる人物であることを見せようとする。 いわゆる,好感度アップのための言動です。
- 示範 社会的に価値のある人物だと見せようとする。 「プロジェクトリーダー」の部分はこれにも当てはまります。 肩書きを主張したり自慢するタイプもこれ。
- 威嚇 権力を行使できる人物であることを見せようとする。 「私を誰だと思っているんだ!お前の首なんて簡単に飛ばせるんだぞ!」なんて脅し文句はまさにこれ。
- 哀願 自分を同情を引く人物であると見せようとする。 不幸自慢をするタイプ。
自己呈示の機能
自己呈示には,相手の抱く自分の印象を操作するという目的以外にもいくつかの機能があります。
①報酬の獲得と損失の回避 自己呈示をすることによって,地位を得たり,他者からの援助を受けたりといった報酬を得ることや,現在の地位を維持したり,持っている資源を守る事にも役立つ。
②自尊感情の高揚と維持 自己呈示によって他者から好意的に評価されれば,自尊感情を高めることができます。 反対に,他者からの非難を自己呈示によって避けることが出来れば自尊感情が下がるのを防ぐことができます。
自尊感情について詳しくは
③アイデンティティの確立 呈示した行動と他者の反応,評価が一致しない場合には,自己概念に従った行動を取ることでアイデンティティの確立に役立つことができます。
アイデンティティについて詳しくは
自己概念について詳しくは
〇自己呈示の内在化
自己呈示は次第に内在化されることで,自己概念やアイデンティティに影響を及ぼします。
自己呈示の内在化は,誰かに見られている場面で顕名で行うことでより促進されます。 スポーツの試合でも,誰にも見られていない時より観客が入った試合の時の方が,選手の成績が良いという例もあります。
他にも,自分でその自己呈示行動を選択したという意識が強いときや,他者から自己呈示を行為的に受け取られたときに自己呈示の内在化は促進されます。
〇自己呈示の明と暗
自己呈示というと,なんとなく「嘘をついている」「演技をしている」というネガティブな印象を持つ人も多いのではないでしょうか。 実際,上で出した自己呈示の種類の例でもネガティブなものを僕も出したりしています。
でも,これまで見てきたように,自己呈示をすることでその言動に見合ったパフォーマンスを出していくという良い側面もあるのです。
それを一番実践しているのは,サッカーの本田圭佑選手ではないでしょうか。
あまりに不遜すぎる自己呈示は相手を不快にさせますが,自分の可能性を高めていくために時として「大口をたたく」ことも必要なのかもしれませんね。
療育へのまなざし
大人の自己呈示と子どもの自己呈示を考えたときに,多少異なることがあります。
大人の自己呈示の場合,多くの場合それは他者に対して自分をよく見せたいという願いからくるものが多いです。
でも,子どもの場合の自己呈示は,子どもの「こうありたい」という願いの姿である場合も多くあります。
自己呈示は内在化していく過程で自己概念やアイデンティティの形成に影響を与えていきます。 子どもの多少「大口」にも思える自己呈示は,子どもの「こういう人物になりたい」という願望の表れでもあるのです。
そんなせっかくの「大口」を一蹴してしまうのは何とももったいない。 成長の貴重な機会ととらえて,好意的に受け入れてあげたいところです。
さて,発達障害を持つ子の場合では,自分の意見や想いをあけすけに伝える事には長けていても,自己呈示という方略を戦略的に使えない子も多くいます。
自己呈示には,自分をよく見せたいという操作的な意図とは別に,自尊感情の高揚や維持,社会的報酬の獲得と自己の利益になる部分があります。 やりすぎはもちろんよくありませんが,自己呈示を上手く使えることも社会を生きやすくしていくひとつの技です。
日本人の美徳として,自分の事をわざと下げて伝えることが良しとされています。 それでもやはり,子どものころから自分の事を肯定的に伝えられる力やその機会が多くあることは社会的な適応を良くします。
療育の場面でも,その様な機会を設けたり,自分の事を肯定的に伝えられるスキルの練習をすることはとても意味があります。
しかし,反対に自尊感情の傷つきからより自分を大きく見せようと自己呈示を過剰にしてしまうパターンもあります。
その様な場合,今度は自己呈示と現実とのギャップが開きすぎたり,他者から否定的に取られたりして自尊感情の更なる低下を招くことも。
前者の成長の欲求から出る自己呈示と,後者の自己の傷つきから出る自己呈示とでは,心理的な意味合いが異なります。 その点は,子どもと向き合う際にしっかりと見極めていきたい部分です。
ただ,前者後者いずれの場合にしろ,自己呈示を「大口」や「嘘,演技」だと切り捨ててしまうのではなく, 背景にある自己を守り育てたいという思いをくみ取り,支持的に寄り添っていく事が大切です。